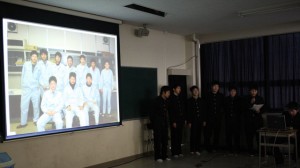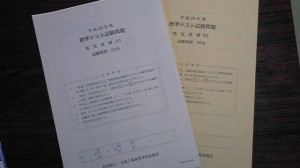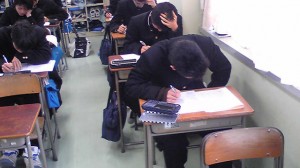昨日(2月4日)、電気科課題研究発表会を電気科実習室にて実施しました。3年生が6班に分かれて1年間研究した成果を、電気科・電気情報科1~3年生の前で報告しました。校長先生・教頭先生ほかの先生も見に来てくださり、緊張していました。
今年のテーマは次の6件でした。
・表計算マイクロソフトエクセル
・バレーボールサーフへマシンの製作
・実習教材の製作
・マイコンカーラリー
・UFOキャッチャーの製作
・仁科ロボットコンテスト
‘ホームルーム’ カテゴリーのアーカイブ
電気科課題研究発表会
2009年2月5日 木曜日標準テスト
2009年1月31日 土曜日第7回高大連携事業
2009年1月28日 水曜日3年間の最終授業
2009年1月27日 火曜日白ポスト製作により感謝状
2009年1月22日 木曜日 1月19日、電子機械科製作の白ポスト贈呈に対し、笠岡市・浅口市及び里庄町青少年補導連絡協議会(会長笠岡市長 高木直矢氏)より感謝状をいただきました。この白ポストは、投入箱が、直径約45センチ、高さ60センチで、全高約90センチメートルの丸形ものと、縦横約45センチ、高さ60センチ、全高約90センチの角形のものの、各1基です。
白ポストは管内の11箇所に設置され、青少年に有害な雑誌・DVD等を回収しています。年間では約600程も回収しています。主に設置されているのは、JR駅や、バスステーション、多くの人が通行する場所なのですが、屋外のところが多く、だんだんと痛んできます。本校ではかなり以前から白ポストを製作し、同協議会へ寄贈してきました。今回その行為に対し、感謝状を頂いたものです。
ポストの製作は、電子機械科3年の課題研究「難しい溶接班」の井上智彰君、橋本和希君、八杉 亮君、山下洋紀君、阿部将太君、岡 正紀君の6名があたりました。彼らの感想です。
材料の大きさから、できるだけ無駄が無いよう、大きさを計算し、最大寸法で取れるよう工夫しました。また、屋外のため、フタに雨が溜まらないよう、傾斜をつけました。そして、フタも簡単に外れないようダブルナットとし、安全のために袋ナットも使用しました。
製作で苦労したことは、溶接です。練習では上手くできても、いざ製品となると、穴があいたり溶け込み不良があったりで大変でした。また、ふたは斜めの部分にはまるため、横の部分の角度はそのままでは使用できず、製作には非常に苦労しました。丸いほうは、2、3ミリメートルの鉄板を、ローラできれいに曲げるのが大変でした。
自分たちが一生懸命作ったものが、社会のために役立つことは、大きな喜びです。
21日の山陽新聞、22日の朝日新聞にも掲載していただきましたのでご覧ください。
第6回コラボレーション事業開催
2009年1月22日 木曜日第6回高大連携事業
2009年1月21日 水曜日全国製図コンクールで最優秀特別賞
2009年1月20日 火曜日「全国製図コンクール」(全国工業高校長協会主催)の電気系で、最優秀特別賞を受賞したE3幡司君の記事を、本日付の山陽新聞 笠岡井原圏版に掲載して頂きました。下記のURLからもご覧いただけます。
http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2009/01/20/2009012010121756012.html
第5回高大連携事業
2009年1月10日 土曜日電気情報科2年生9名は、福山大学との高大連携事業第5回目を行いました。
今回は、福山大学へお邪魔して大学の設備を借りてのお勉強です。
最初に、FPGA(Field Programmable Gate Array)というプログラミングすることができるLSIの使い方を習いました。VHDL(Very Highspeed Integrated Circuit[VHSIC] Hardware Discription Language)というプログラミング言語で論理回路を記述し、入出力端子に信号を割り付けると論理ICとして動作します。いままでは、ブレッドボードでたくさんの配線をしていたのが嘘のような手軽さです。今回は、半加算器の回路を作りました。
次に、プリント基板PCB(Printed Circuit Board)の設計方法を練習しました。OrCADというソフトを使用して、オペアンプ回路基板の設計をしました。同じ回路図なのに、班ごとに、個性的なパターンが出来上がって面白かったです。
最後に、研究室を案内していただき、最先端の研究内容にも触れることができて、有意義な訪問になりました。