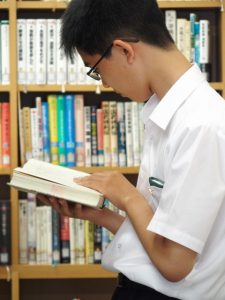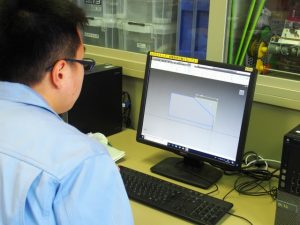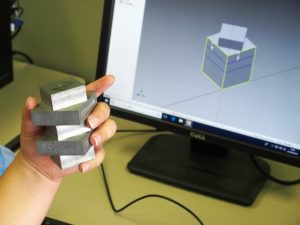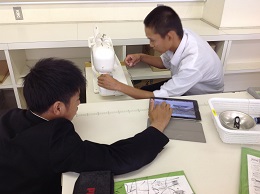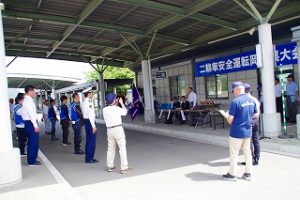平成30年度 第52回 中国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会
平成30年6月16~17日 広島県立戸手高等学校 体育館
開会式
大会委員長「広島県立戸手高等学校 校長先生」が大会のあいさつ。
「選手のみなさん おはようございます」の後・・・
当然、全ての参加校選手が「おはようございます」のあいさつ。
ただ・・・笠岡工業高校の選手は「おはようございます」の後、全員そろって「お辞儀・礼」をしました。
指導者として、そのすばらしさに鳥肌が立ちました。
そしてその瞬間「こいつら・・・勝つな!」と確信しました。
逆転負けして、悔しさに涙していた「原田絃希」が、真っ先に口にしたのは「先生!団体はどうですか?すみません(泣)」
笠工同士の熾烈なメダル争いに負けウルウルしていた選手も、よし!来年!!!と気持ちを切り替え。残りの選手に精一杯の応援。「チーム笠工ウエイトリフティング部」
結果は こうだ!!!!!みんな笑ってる。
【学校対抗の部】
優勝 岡山県立笠岡工業高等学校 得点106点(2年ぶり5回目)
2位 島根県立出雲農林高等学校 得点 85点
3位 岡山県立水島工業高等学校 得点 83点
【個人の部】
この大会も終わってみれば学校対抗では、2位と大差になりましたが・・・相手のミスや、ラキーが重なりこの結果となりました。「厳しい優勝争いになるな・・・と思っていましたが、試合は終わるまでわからない」と選手は自分の順位も記録も捨て、貪欲に1点の団体得点に執着したまさに「チーム力」の優勝でした。思い起こせば・・・昨年8月に今の新チームとなった時、2017年8月25日のブログにこう書き込んでいました。
『新しいキャプテンになった「原田絃希」を中心に発進です。新チームに優しい監督から与えられた最低のノルマは、「中国大会 団体優勝」 新チーム 原田絃希 丸は、厳しい船出となります。頑張れ! きっとノルマは達成できる。達成させる(笑)』
1年前 どうみても優勝できるチームではなかったのに、やつらホンマに優勝しやがった!許されるなら、応援に駆けつけた選手以外の部員を含め21人全員に「あっぱれカード」です。
そして、今回も多くの保護者・家族の方々に遠路会場まで駆けつけていただきました。監督では与えられない「追加の力」は、保護者・家族の皆様の一声です。本当にありがとうございました。
おかげさまで 笠岡工業高等学校は、優勝しました。
さあ、来年度の中国高等学校選手権は今日から始まりました。来年の大本命は「山口県 下関国際高校」です。笠工はマジめっちゃ厳しい状況ですが、1年後何が起こるのか・・・?監督の頭の中には「連覇」しかない。(笑)



























 放課後の教室掃除
放課後の教室掃除